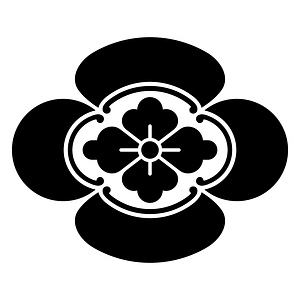五輪塔の深い意味とは?古代から続く日本のお墓の歴史と仏教の影響を解説

皆様こんにちは。山形で墓石・石材加工を承っております、有限会社白田石材です。
お墓参りの際、古くからある墓地などで、独特な形をした石塔をご覧になったことはありませんか?丸や四角など、異なる形の石が積み重なったそのお墓は「五輪塔(ごりんとう)」と呼ばれます。
「どうしてあのような形をしているのだろう?」「どんな意味が込められているの?」
そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。実はこの五輪塔、ただの古い形式のお墓というだけではなく、日本の歴史や仏教の宇宙観が深く関わった、非常に意味深い供養塔なのです。
今回は、古代からの日本のお墓の変遷をたどりながら、五輪塔の成り立ちとその深い意味について、石材店の視点から分かりやすく解説いたします。

古代日本のお墓の始まりと仏教の伝来
日本の古代のお墓は、権力者の力を示す巨大な「古墳」に代表されるように、亡くなった方を埋葬し、その上に土を盛る「土葬」が主流でした。そこには、自然への畏敬の念や、集落の安寧を願う想いが込められていたと考えられています。
大きな転機となったのが、6世紀頃に大陸から伝わった仏教です。仏教は、死後の世界や輪廻転生の考え方と共に、**「火葬」**の文化をもたらしました。また、お釈迦様のご遺骨(仏舎利)を納めた塔「ストゥーパ(卒塔婆)」を礼拝する信仰も伝わります。
この「火葬」と「塔」への信仰が、日本の弔いの形を大きく変え、後の五輪塔誕生の土台となっていくのです。
五輪塔の誕生と密教思想
五輪塔が誕生したのは、平安時代の後期(11世紀~12世紀頃)とされています。特に、**真言宗や天台宗といった「密教」**の教えが大きく影響しています。
密教では、この世界のあらゆるものは**「地(ち)・水(すい)・火(か)・風(ふう)・空(くう)」**という5つの要素(五大)から成り立っていると考えられています。そして、この宇宙の真理そのものを表す仏様が、**大日如来(だいにちにょらい)**です。
五輪塔は、この「五大」思想を形にしたものであり、塔そのものが大日如来の身体、つまり宇宙そのものを象徴する、非常に神聖な供養塔として生まれました。当初は天皇や貴族、有力な武士など、高い身分の人々の墓石や供養塔として建立され、故人の追善供養のために建てられました。
五輪塔が示す宇宙観「地・水・火・風・空」
五輪塔は、下から順番に形の違う5つの石で構成されています。それぞれが「五大」の要素を表し、仏様の世界観を示しているのです。
- 地輪(ちりん) - 方形(四角)
- 一番下の四角い石。大地を表し、安定や堅固さを意味します。
- 密教の梵字では「ア(a)」字が刻まれます。
- 水輪(すいりん) - 円形(丸)
- 下から二番目の丸い石。水を表し、生命の源や変化を意味します。
- 梵字は「ヴァ(va)」字が刻まれます。
- 火輪(かりん) - 三角形(宝形)
- 屋根にあたる笠の部分。三角形で火を表し、情熱や力を意味します。
- 梵字は「ラ(ra)」字が刻まれます。
- 風輪(ふうりん) - 半月形
- 笠の上の受け皿のような部分。半月形で風を表し、成長や動きを意味します。
- 梵字は「カ(kha)」字が刻まれます。
- 空輪(くうりん) - 宝珠形
- 一番上の玉ねぎのような形の部分。空間や完成、仏の悟りの境地を表します。
- 梵字は「キャ(ca)」字が刻まれます。
これら「ア・ヴァ・ラ・カ・キャ」の梵字は、大日如来の真言(呪文)にも通じます。
つまり五輪塔とは、亡くなった方が「地・水・火・風・空」という宇宙の構成要素に還り、大日如来と一体となって安らかに成仏してほしいという、壮大で深い祈りが込められた形なのです。

宗派を超えて広まった五輪塔
鎌倉時代に入ると、五輪塔は宗派の垣根を越えて、武士や庶民の間にも広く使われるようになりました。その背景には、身分や宗派に関わらず「誰もが等しく成仏できる」という思想が人々の心に響いたからだと言われています。
江戸時代には、一般的なお墓の形式として広く定着しました。現在私たちがよく目にする「和型墓石」も、実はこの五輪塔の思想を受け継いでいると言われ、その名残を見ることができます。
まとめ
五輪塔は、単なる石塔ではありません。古代からの日本の死生観と、大陸から伝わった仏教の壮大な宇宙観が見事に融合して生まれた、祈りの結晶です。その形一つひとつに、故人が大自然に還り、仏様の世界で安らかに眠ることへの願いが込められています。
私たち有限会社白田石材は、こうした伝統的なお墓に込められた先人たちの想いを大切に受け継ぎながら、お客様一人ひとりのご供養の心に寄り添ったお墓づくりを心がけております。
五輪塔の建立はもちろん、お墓に関するご相談は、どうぞお気軽に私たち「白田石材」までお問い合わせください。